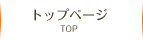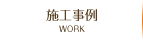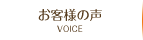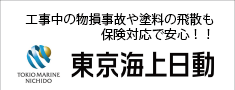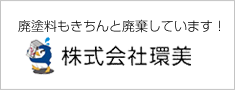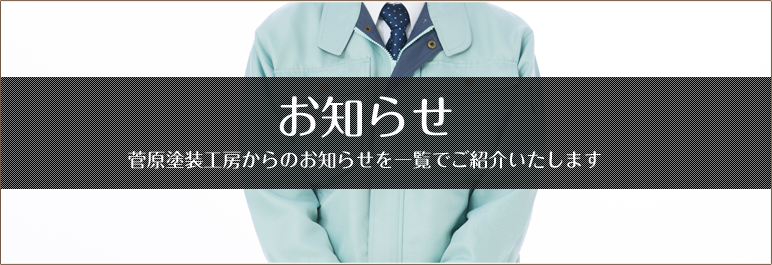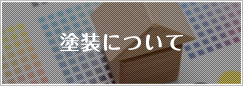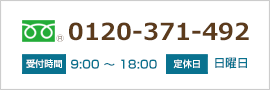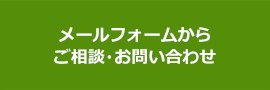著者:有限会社菅原塗装工房

外壁塗装の手順を調べていて、こんな疑問を感じたことはありませんか?
「どの工程で失敗しやすいのか分からない」「塗装の順番や乾燥時間ってどれくらい必要?」「下塗りと上塗りって本当に違いがあるの?」といった声は、これまで多くの相談で耳にしてきました。実際、外壁塗装は単なる色塗りではなく、塗料の選定から足場の設置、下地処理、高圧洗浄、塗膜の構成、シーリング補修、そして上塗りまで、すべてが密接に連携してはじめて高品質な仕上がりにつながります。
とくに2025年現在、国土交通省の外装メンテナンス指針でも「施工の流れと適切な乾燥時間」が耐久性に大きく関わると強調されています。放置すれば塗膜の劣化が早まり、10年持つはずの塗料がわずか5年で剥がれるというケースもあるのです。これは見積もりや工事の段取りで差が出る、いわば「業者選びの盲点」と言えます。
この記事では、外壁塗装の正しい手順とともに、一般的な工程表には載らないプロ目線のポイントも含めて、塗り残しを防ぎ仕上がりを格段に美しく保つ方法を紹介します。最後まで読むと、見積書の読み方や業者選定時のチェックポイントまで理解でき、将来のメンテナンスコストもぐっと抑えられるでしょう。
高品質な外壁塗装で安心の住まいづくりを実現します – 有限会社菅原塗装工房
外壁塗装をはじめ、屋根塗装や内装塗装、防水工事など幅広い塗装工事に対応しております。お客様のご要望や建物の状態に合わせて、最適な塗料と工法を選定し、高品質で長持ちする仕上がりをご提供いたします。職人直営の強みを活かし、中間マージンを抑えた適正価格での施工が可能です。仕上がりの美しさはもちろん、耐久性や防水性にもこだわり、安心して暮らせる住まいづくりをお手伝いいたします。丁寧な対応と確かな技術でご信頼にお応えいたします。
外壁塗装の手順を理解する前に知っておくべき基本情報
外壁塗装とは?外壁材と耐用年数の関係性を知る
外壁塗装は建物を保護し、美観を維持するために欠かせないメンテナンスの一つです。しかし、外壁塗装を検討する際に見落とされがちなのが、外壁材の種類によって必要な塗装のタイミングや使う塗料が異なるという点です。一般的な住宅で使用されている外壁材には、サイディング、モルタル、ALC(軽量気泡コンクリート)などがあります。これらの素材はそれぞれ特性が異なり、耐用年数も変わってきます。
たとえば、日本の戸建て住宅で最も多く使われている窯業系サイディングは、素材自体の耐久性は30年以上あるとされていますが、表面の塗膜は約10年で劣化します。そのため、10年ごとを目安に塗り替えを検討するのが一般的です。一方、モルタル壁は、素材の性質上ひび割れ(クラック)が起きやすく、塗膜でしっかりと保護しないと雨水の侵入や劣化の原因となります。
下記では、代表的な外壁材の種類と塗装の目安時期をまとめました。
| 外壁材の種類 | 特徴 | 推奨される塗り替え周期 |
| 窯業系サイディング | 一般住宅で最も普及。防火性に優れるが塗膜劣化に注意 | 約10年ごと |
| モルタル | 左官仕上げで高級感あり。クラックが発生しやすいため保護が重要 | 約8〜10年ごと |
| ALCパネル | 断熱性と耐火性に優れるが防水性に劣る。シーリングと塗装が必須 | 約10年ごと |
| 金属サイディング | 軽量で施工しやすく、防水性に優れるがサビ対策が必要 | 約10〜15年ごと |
素材ごとに必要な塗装タイミングや適切な塗料の種類が異なるため、自宅の外壁材を把握したうえでメンテナンス計画を立てることが重要です。特に、サイディングの場合は目地のシーリングの打ち替えもセットで考える必要があり、塗料の選定も耐久性・遮熱性・防汚性など性能を比較しながら進めるのが理想です。
加えて、塗装時には外壁材に適した下地処理を行わないと、せっかくの高性能な塗料も十分に効果を発揮しません。例えば、シーラーやプライマーの塗布を省略すると、密着不良や塗膜剥離を招く可能性が高まります。塗料の選び方とあわせて、下塗りの工程を正しく理解することも忘れてはなりません。
外壁塗装が必要になる代表的な劣化サイン
外壁塗装はただ見た目を美しくするためだけでなく、建物を守るための防御手段です。適切なタイミングでの塗り替えが重要であるにも関わらず、劣化サインを見逃してしまうケースは多くあります。特に以下のような兆候が見られる場合は、外壁塗装の検討が必要です。
もっとも一般的なのが、チョーキング現象です。これは外壁を手で触ったときに白い粉がつく現象で、塗膜が紫外線や雨風で分解されている証拠です。この状態を放置すると、防水機能が低下し、建物内部への水の侵入リスクが高まります。
次に注意すべきは、ひび割れ(クラック)です。0.3mm以上の幅があるひび割れは「構造クラック」とも呼ばれ、水の侵入だけでなく建物自体の強度に影響を与える可能性があります。モルタル外壁では特にこの傾向が強く、早期発見と補修が求められます。
また、シーリング材のひび割れや剥がれも見逃せません。サイディングボードのつなぎ目に充填されているシーリングは、建物の動きに追従しながら防水の役割を果たしますが、紫外線や経年劣化により硬化してしまい、ヒビ割れや剥離を起こします。このまま放置すると、外壁の内部に水が回り、構造部分の腐食やカビの発生につながる恐れがあります。
そのほか、外壁の一部に苔やカビが発生している、塗膜が剥がれてきた、色あせが目立つなども劣化の兆候です。外観がくすんで見えるだけでなく、これらは塗膜の防水性が失われている証拠でもあります。特に北側の外壁や日陰の多い場所では湿気がこもりやすく、早期に発生する傾向があるため、定期的な点検が欠かせません。
このような症状が一つでも当てはまる場合は、外壁塗装の時期に差し掛かっていると考えてよいでしょう。塗装を先延ばしにすると、補修範囲が広がり工事費用も増大します。定期的なメンテナンスと早期の対応が、住まいの寿命を延ばす大切なポイントです。
外壁塗装の全工程を徹底解説!
工事開始前の準備!現地調査、見積書の確認ポイント
外壁塗装工事を開始する前には、現地調査と見積書の確認が重要な工程です。現地調査では、外壁の材質、劣化状況、クラックの有無、既存塗膜の種類、シーリングの劣化度などが詳しく調査されます。この調査結果をもとに塗装の範囲や使用する塗料の種類、補修が必要な箇所が決定されるため、プロによる丁寧な調査が欠かせません。
見積書では、項目が具体的に記載されているかを確認することが大切です。たとえば「一式」と記載されているものには注意が必要で、塗装面積の㎡数、使用塗料のグレード、下地補修の範囲、高圧洗浄の有無などが明確に記載されているかをチェックしましょう。契約前に複数業者から見積もりを取り、相場と照らし合わせて内容に過不足がないかを確認することで、適正価格かつ高品質な施工が可能になります。
足場設置と飛散防止シートの設置
外壁塗装の工程において、最初の作業となるのが足場設置と飛散防止シートの設置です。足場は職人の安全確保と作業効率を高める目的があり、設置は仮設工事業者が行います。足場を組むことで細部まで丁寧に塗装でき、事故や施工ミスのリスクを低減できます。
また、塗料の飛散を防ぐために飛散防止シート(メッシュシート)を設置するのも重要な作業です。これにより近隣住宅や車両への塗料の飛散を防ぎ、トラブルを回避できます。近隣住民への事前挨拶も含め、配慮のある施工計画が求められます。
高圧洗浄の目的と乾燥時間の注意点
塗装前には必ず高圧洗浄を行い、外壁表面の汚れや古い塗膜、カビ、コケなどを除去します。これを怠ると新しい塗料がしっかり密着せず、剥がれやムラの原因となります。高圧洗浄には高圧洗浄機が用いられ、通常は100~150kg/cm²程度の水圧で洗浄が行われます。
洗浄後には外壁をしっかり乾燥させる必要があります。乾燥時間は天候や気温にも左右されますが、目安としては最低でも24時間以上。梅雨時や冬季はさらに長めに乾燥期間を設けるのが理想です。この工程を丁寧に行うことで、塗装後の仕上がりや耐久性に大きな差が生まれます。
下地処理とシーリング処理の正しい順番
塗装前の下地処理は、塗料の耐久性と美観を左右する重要な工程です。劣化した部分の補修、ひび割れ(クラック)の埋め戻し、旧塗膜の剥がれた部分の整形などが含まれます。これに続いてシーリング処理が行われますが、「打ち替え」か「増し打ち」かの判断が重要です。
打ち替えは古いシーリング材を撤去して新たに充填する方法で、より確実な防水効果が期待できます。対して増し打ちは既存シーリングの上から重ねるだけのため、劣化が進んでいる場合には適しません。使用するシーリング材の種類や施工方法によっても耐用年数が変わるため、施工前の説明をしっかり確認しておくことが求められます。
塗装の基本3工程(下塗り・中塗り・上塗り)と塗料の選び方
外壁塗装は「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗りが基本です。下塗りは塗料の密着性を高める役割を担い、フィラーやシーラー、プライマーなどの専用塗料が使用されます。中塗りと上塗りには色や艶、機能性をもたせるための塗料を使用し、塗膜の厚みを出して耐候性や美観を強化します。
塗料の選び方も重要で、アクリル系・ウレタン系・シリコン系・フッ素系・無機系といったグレードごとの特性とコストを理解する必要があります。例えば、フッ素系は高価ですが耐久性が非常に高く、トータルコストを抑えたい方には最適です。
施工後の検査・清掃・足場解体・最終引き渡しの流れ
すべての塗装工程が終了したら、最終的な品質確認と清掃作業が行われます。施工会社によっては「自主検査」および「施主立ち会い検査」が用意されており、色ムラや塗り残し、シーリングの不備、養生のはがし残しなどを細かくチェックします。特に外壁の塗り分けがある場合は、ラインのにじみなどが無いかも重要な確認ポイントです。
その後、足場の解体作業と敷地内の清掃が行われ、工事中に使用した資材やゴミなどがすべて撤去されて引き渡しとなります。工事完了後には保証書や施工写真、使用塗料の情報をまとめた完了報告書が提出されることが一般的です。
こうした書類は万が一の不具合や塗膜の剥がれなどが起きた際の保証申請に必要となるため、必ず保管しておくようにしましょう。高品質な施工を提供する業者であれば、施工前後の写真付きで丁寧な説明を行い、今後のメンテナンスについてのアドバイスもしてくれます。
工事の最終段階こそ、信頼できる業者かどうかを見極める最大のチャンスです。最後まで安心して任せられるよう、細部まで確認し納得して引き渡しを受けましょう。
外壁塗装にかかる日数と季節の選び方!雨季や冬季は避けるべき?
外壁塗装の日数は平均何日?工程別の目安と実例
外壁塗装にかかる日数は、一般的な戸建住宅でおおよそ10日から14日が目安とされていますが、これはあくまで天候に恵まれ、スムーズに作業が進んだ場合の話です。実際には、乾燥時間や天気の影響、建物の構造、塗装面積によって大きく変動します。特に「下塗り」「中塗り」「上塗り」の各工程にはしっかりとした乾燥時間が必要であり、この時間を短縮すると塗膜の耐久性が著しく低下してしまう可能性があります。
また、シーリング工事の有無や屋根塗装との同時施工などによっても日数は異なります。以下に工程別の日数の目安を表にまとめました。
| 工程項目 | 平均日数(目安) | 注意点例 |
| 足場の組立と設置 | 1日 | 仮設工事により騒音や振動が発生 |
| 高圧洗浄 | 1日 | 乾燥時間に24時間以上が必要 |
| 養生作業 | 1日 | 窓や玄関の養生で通風に注意 |
| シーリング補修 | 1日〜2日 | 打ち替え作業と乾燥時間に要配慮 |
| 下塗り | 1日 | プライマーの乾燥をしっかり確認 |
| 中塗り・上塗り | 2日〜3日 | それぞれ乾燥時間が必要 |
| 検査・補修・清掃 | 1日 | 最終チェックで仕上がりを確認 |
| 足場解体 | 1日 | 周囲への安全配慮が必要 |
このように、工程が多岐に渡るため、施工会社によっては前後に余裕を持った工期を提案することがあります。特に梅雨や台風シーズンは工期の遅れも発生しやすく、天候に左右されるリスクがあるため、契約時には「予定工期」と「想定される延長日数」について明記しておくと安心です。
外壁塗装に適さない月とは?気温・湿度・乾燥時間の関係
外壁塗装において季節の選び方は非常に重要であり、塗料の性能や仕上がりに直接的な影響を与える要素となります。日本の気候を考慮すると、もっとも避けたい時期は「梅雨時期(6月中旬〜7月中旬)」と「厳冬期(1月〜2月)」です。この時期は降雨日数が多く、気温が低く湿度も高くなるため、塗料の乾燥に必要な条件を満たさないことが多く、塗り直しや剥離の原因になります。
塗料メーカーの多くは施工条件として「気温5度以上」「湿度85%未満」を推奨しています。これは塗料の密着性と硬化反応に関係しており、これを下回る気候下での施工は本来避けるべきとされています。特に冬季は、日照時間の短さや朝露・霜の影響により、作業開始時間が遅れることが多く、作業効率も下がります。
気象庁の統計データに基づけば、関東地方で比較的施工に適した月は3月〜5月、または9月〜11月です。夏場の8月も晴天率は高いですが、高温多湿のため塗装面に気泡が生じるリスクがあるため、日中の作業時間を調整する工夫が求められます。
また、最近では温暖化の影響で季節変動が読みにくくなってきているため、気象データを参考にしながら現場ごとに柔軟な判断が必要です。業者に相談する際には「この時期の施工は問題ないか」「過去にトラブルがあったか」などの確認をするとより信頼性が高まります。
まとめ
外壁塗装を成功させるためには、正しい手順と工程を理解することが欠かせません。下塗りから上塗りまでの塗装工程や、シーリング処理、高圧洗浄、足場設置といった各作業は、それぞれが密接に関係しており、一つでも手を抜けば仕上がりや耐久性に大きな影響を与えます。特に塗膜の密着性や塗料の乾燥時間は、外壁の寿命を左右する重要な要素です。
また、施工にかかる日数や費用は、天候や建物の劣化状況によって変動します。たとえば梅雨時期は乾燥に時間がかかり、工期が延びる傾向にあるため、計画段階で余裕を持ったスケジュールを立てることが求められます。足場や仮設シートの設置、高圧洗浄などの工程にも注意を払い、信頼できる業者選びが必要不可欠です。
DIYによる塗装は費用を抑える手段の一つですが、安全性や仕上がり、再塗装の手間を考えると、専門業者への依頼が結果的にコストを抑える場合もあります。塗料の種類や施工箇所に合った下地処理、モルタルやサイディングといった素材に対応した技術は、経験豊富な職人でなければ難しいこともあります。
この記事では、外壁塗装の流れや手順を詳しく解説しながら、失敗を防ぐポイントや注意点を丁寧に紹介しました。今後の塗装計画を立てる際には、今回ご紹介した情報をもとに、費用や作業内容、季節の選び方までしっかりと比較検討し、後悔のない選択をしていただければと思います。適切な知識と準備があれば、仕上がりの美しさと耐久性を兼ね備えた理想の住まいが実現します。
高品質な外壁塗装で安心の住まいづくりを実現します – 有限会社菅原塗装工房
外壁塗装をはじめ、屋根塗装や内装塗装、防水工事など幅広い塗装工事に対応しております。お客様のご要望や建物の状態に合わせて、最適な塗料と工法を選定し、高品質で長持ちする仕上がりをご提供いたします。職人直営の強みを活かし、中間マージンを抑えた適正価格での施工が可能です。仕上がりの美しさはもちろん、耐久性や防水性にもこだわり、安心して暮らせる住まいづくりをお手伝いいたします。丁寧な対応と確かな技術でご信頼にお応えいたします。
よくある質問
Q. 外壁塗装の費用は手順によってどれくらい変わるのですか?
A. 外壁塗装の手順ごとに費用は明確に異なります。たとえば足場設置には20万円前後、高圧洗浄や養生などの仮設作業で5万円から10万円、塗料はグレードによって1平方メートルあたり1500円から3500円と大きく差が出ます。さらにシーリングの打ち替えや下地補修など、下地処理の有無でも費用が増減します。全体の施工手順に対してどの作業が含まれているかを見積書で確認することで、相場と照らし合わせた判断が可能になります。
Q. 外壁塗装の工程ごとの平均的な日数はどれくらいですか?
A. 一般的な延床面積30坪前後の戸建住宅では、足場設置に1日、高圧洗浄に1日、乾燥に1日、下地処理とシーリング工事で2日、塗装(下塗り・中塗り・上塗り)で3日、最終検査と足場解体に2日ほどかかります。合計すると10日前後が平均的な日数とされますが、梅雨や冬場は乾燥時間が長くなるため14日以上かかるケースもあります。気象条件による遅延リスクを考慮したスケジューリングが重要です。
Q. 外壁材によって塗装手順は変わりますか?モルタルとサイディングの違いは?
A. はい、外壁材によって下地処理や塗料の選定が大きく変わります。モルタル外壁ではクラック補修やフィラーの使用が必須で、下塗りにはシーラーよりも密着性の高いフィラー系塗料が使われます。一方、窯業系サイディングは既存の塗膜やシーリングの状態により、打ち替えや増し打ちの判断が必要になります。塗料も素材に適したアクリルシリコン系やフッ素系など、グレードと機能性を合わせた選定が欠かせません。
Q. DIYで外壁塗装する場合、必要な道具と予算はどのくらいですか?
A. DIYで外壁塗装を行う場合、最低限必要な道具としてローラー、ハケ、マスキングテープ、養生シート、塗料、シーラー、高圧洗浄機、脚立または足場などが必要になります。仮に20坪程度の外壁を塗装する場合、塗料に3万円から6万円、足場代行業者の依頼で15万円前後、その他養生や工具類で3万円から5万円の出費が見込まれます。安全性や耐久性を考慮すると、合計で25万円から30万円の予算は見積もっておくべきです。特に足場なしの高所作業は事故リスクが高いため、自己判断には注意が必要です。
会社概要
会社名・・・有限会社菅原塗装工房
所在地・・・〒252-0235 神奈川県相模原市中央区相生3-13-10
電話番号・・・0120-371-492